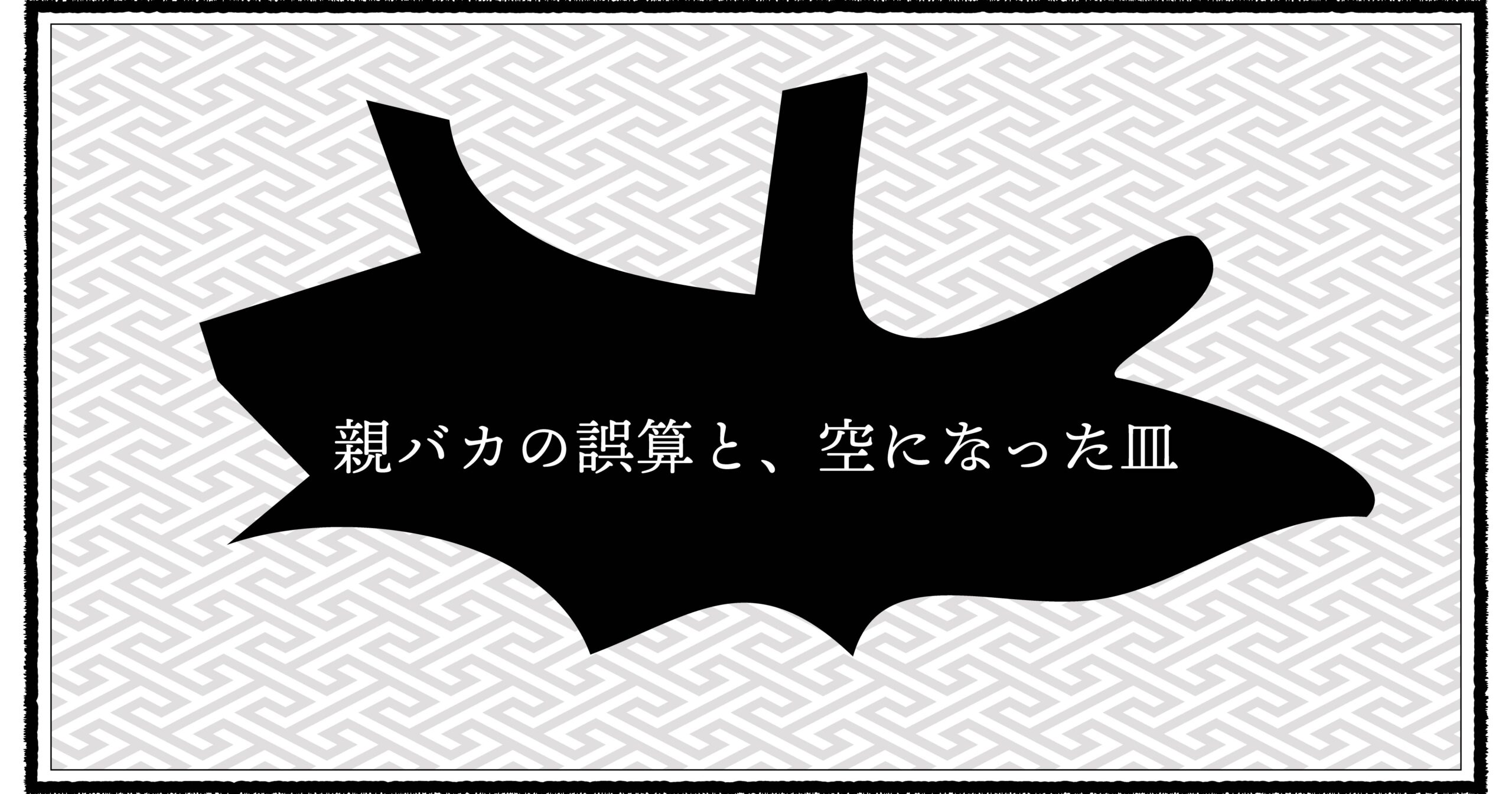離乳食を始めたばかりの頃、息子は何を出しても黙って食べていた。
「好き嫌いがない子だな」
「これは将来有望だ」
私はずいぶん大きなことを言っていた気がする。
今なら分かる。
あれは寛大だったのではない。
まだ反撃の術を知らなかっただけだ。
最近は違う。
気に入らなければ「ブーッ」と見事に吹き返す。
しかも視覚審査つき。
色味や形状が気に入らなければ、口は一ミリも開かない。
「ほら、おいしいぞ」
大げさに食べてみせるが、息子は無表情でこちらを見る。
その目は静かに語っている。
――なら全部どうぞ、と。
食卓に残るのは、冷めた食事と、私の見立て違いだ。
そこへ何も言わず手を伸ばすのが、妻である。
「もったいないじゃない」
そう言って、息子の皿を迷いなく平らげていく。
私の葛藤は、だいたい二口で片づく。
好き嫌いなく食べていた“奇跡の時代”は終わった。
いまは、拒否と様子見と、時々あきらめの繰り返しだ。
空になった皿を見ながら思う。
私も昔、同じことをしていたのだろう。
その後ろで、誰かが静かに食べてくれていたのかもしれない。
皿は、今日もきれいに空になった。