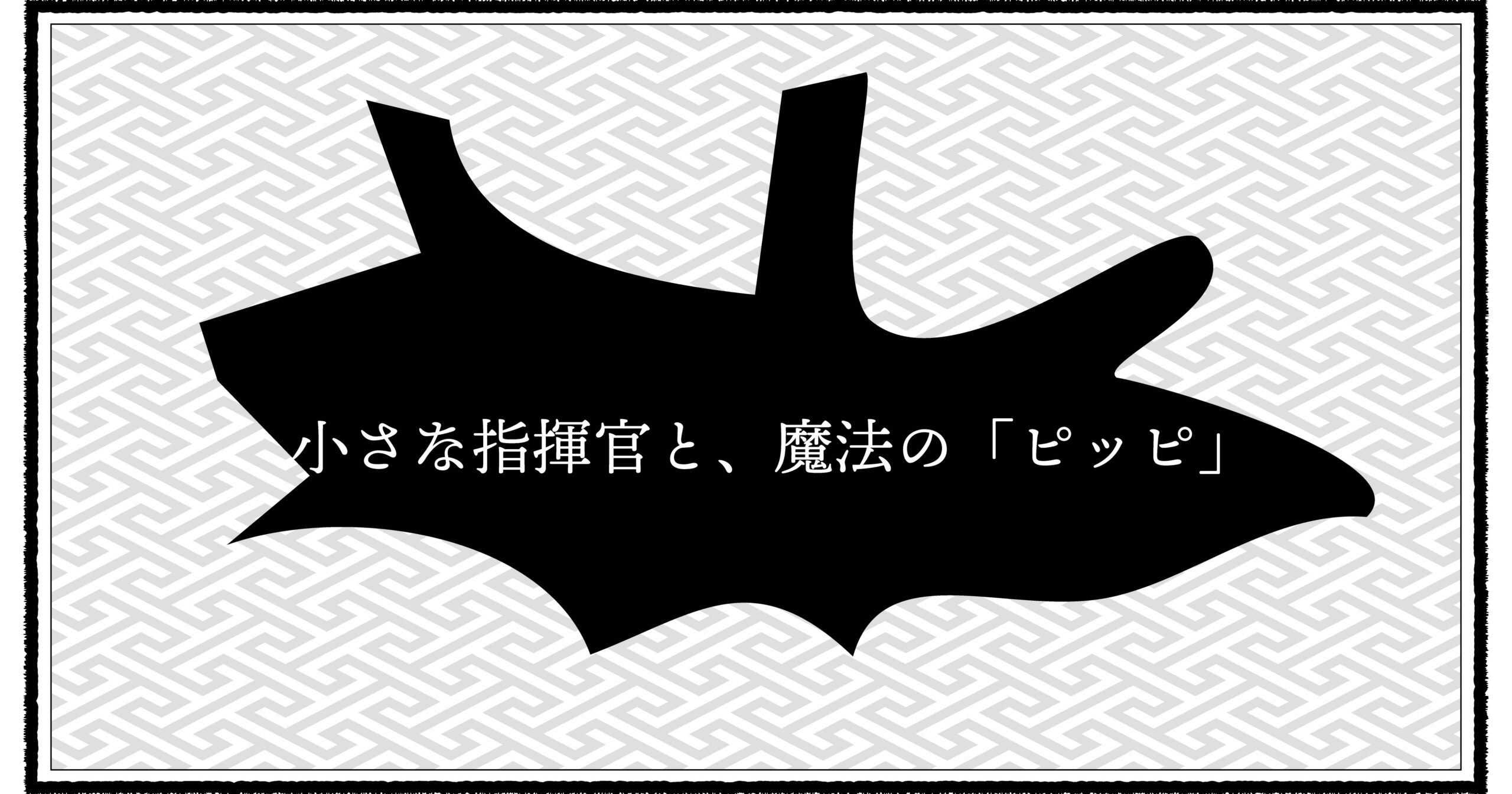一歳の息子は、それを「ピッピ」と呼ぶ。
テレビのリモコンのことだ。
彼にとってピッピは、退屈な日常を一瞬で塗り替える道具らしい。
手に取ったが最後、迷いなく赤い「YouTube」のボタンを狙い撃つ。
ただし、そこから先はまだ一人では完結できない。
画面にロゴが表示されたところで、彼は何事もなかったようにピッピを私に手渡してくる。
「あとはそっちで頼む」と言わんばかりの、淀みのない連携だ。
一度味を占めれば、引き際はない。
見過ぎを案じて私がピッピを隠すと、彼は泣きもせず、ただ私の前に立つ。
そして人差し指を器用に動かし、空中でボタンを押す真似をしてみせる。
完璧なパントマイム。
「ピッピ」
言葉は少ないが、要求は極めて正確だ。
教えた覚えはない。
だが操作の要点だけは、本能で理解しているらしい。
映りの悪いテレビを叩いて直そうとしていた自分の幼少期とは、
どうやら脳の構造からして違う。
事情が違うといえば、CMの扱いもそうだ。
広告が流れた瞬間、息子は画面を見ず、私を見る。
「スキップ」の文字が出るまで待つ、という発想はないらしい。
再び、ピッピが私の鼻先に差し出される。
かつて、CMの時間もまたテレビという娯楽の一部だった。
だが今は、一秒の余白すら長すぎる。
その令和のスピード感の最前線に、
オムツ姿の小さな指揮官が立っている。
私は言われるがまま、命じられるがままにピッピを操作する。
隠しても見透かされ、言葉がなくても動かされる。
どうやら、わが家における私の役割は、
この小さな指揮官の「実行係」に落ち着いたようだ。
「よし、飛ばしたぞ」
満足げに画面を見つめる息子の横顔を眺める。
いつか彼が、スキップの操作まで自分で覚えてしまったとき。
その時こそ、私の本当の引退なのだろう。
それまでは、この不器用な主従関係を、
もう少しだけ楽しませてもらおうと思っている。