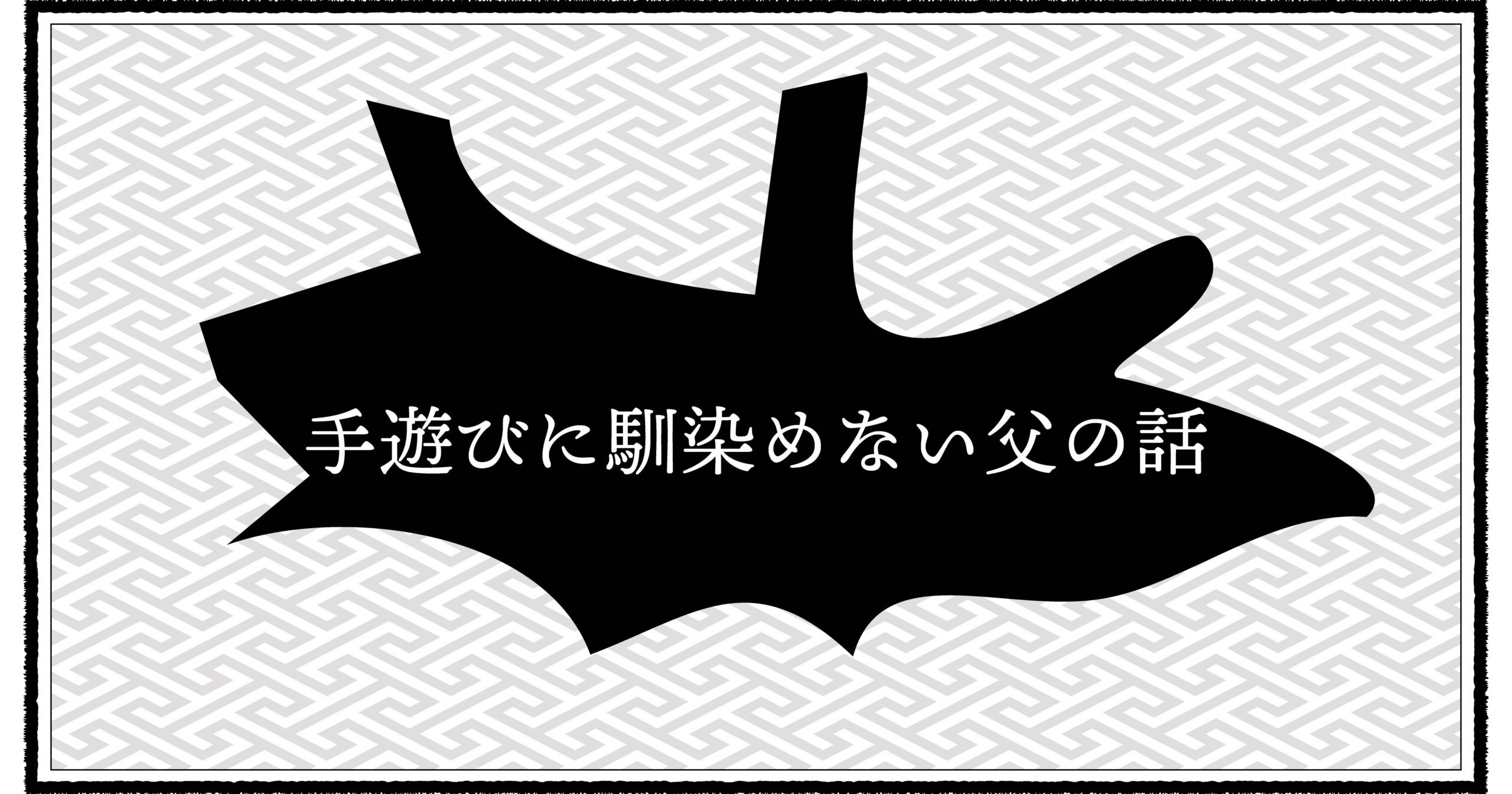「今度、地域の児童館に行かない?」
妻にそう言われた瞬間、頭に浮かんだのは、子どもの頃に通った公民館だった。
薄暗く、床は冷たく、どこか埃っぽい場所。
児童館とは、そういうものだと思い込んでいた。
ところが、現実は容赦なく私の記憶を更新してくる。
辿り着いたそこは、ガラス張りで、光がよく入る。
遊具はどれも洒落ていて、ボーネルンド監修と聞いて納得した。
無料で使っていいのが申し訳なくなるほど、きれいで、整っている。
何度か通ううちに、ここはいい場所だと思うようになった。
息子は汗をかきながら走り回り、
私はそれを少し離れたところから眺めている。
何もしない時間が、こんなに満ち足りているとは思わなかった。
異変は、突然やってきた。
「それでは、みんなで手遊びを始めますよー」
職員さんの声に合わせて、親子が自然と集まっていく。
強制ではない。
だが、この空間で一人だけ輪から外れるほど、私は強くない。
気づけば、お母さんたちに混じって立っていた。
照れを隠しながら、手を動かす。
「グー、チョキ、パーで、なにつくろう」
指先を蟹の形にしながら、ふと思う。
私の手は、本来、仕事をしたり、子どもを抱いたりするためのものだ。
人前で蟹を演じる訓練は、受けてきていない。
息子は楽しそうだった。
それが救いであり、同時に逃げ場を失う理由でもあった。
それ以来、その児童館には足が向かっていない。
場所が悪いわけでも、誰かが悪いわけでもない。
ただ、令和の合理と、私の性分のあいだには、
まだ少し、距離があるだけだ。
その距離をどう埋めるか。
あるいは、無理に埋めなくてもいいのか。
答えは、もう少し先になりそうである。