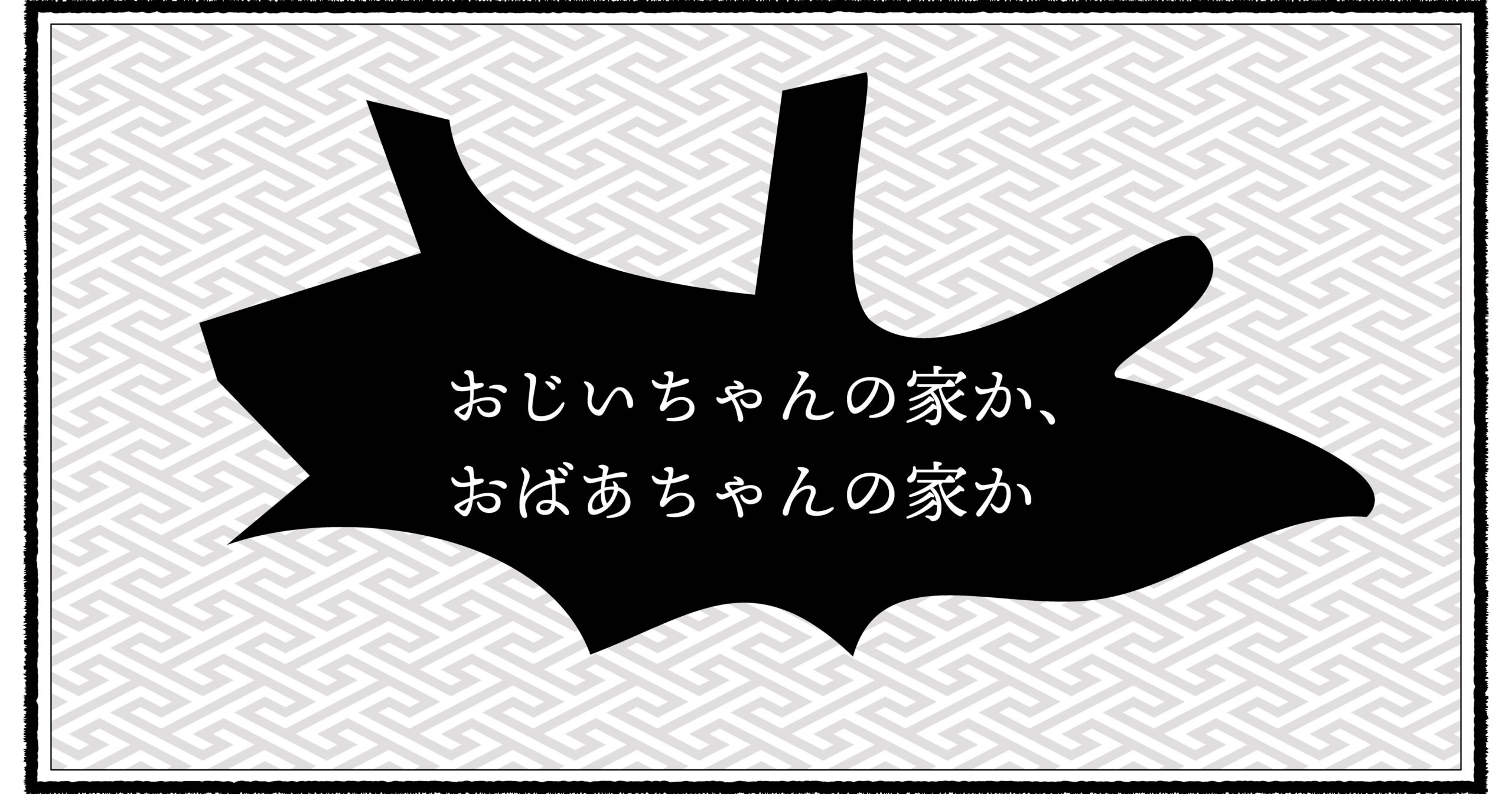「おじいちゃんの家」か、それとも「おばあちゃんの家」か。
実家へ向かう車中、そんな定義のゆらぎに、つい考え込んでしまう。
父という家長への敬意か、それとも家を守ってきた母への親しみか。
そんな理屈を頭の中で並べていると、助手席の妻が、スマホから目を上げずに言った。
「どっちでもいいじゃない」
正論である。
息子にとって、そこは問答無用のパラダイスだ。
到着するやいなや、おばあちゃんは市場の競りにでも参加してきたかのような勢いで、果物を剥きはじめる。
リンゴ、みかん、そしてラ・フランス。
器には山。いわゆる、漫画盛りである。
初めての食感に目を丸くする息子を眺めながら、ふと自分の幼少期を思い出す。
果物を「剥いてもらう」という行為が、どれほど贅沢なものだったか。
その本当の価値を知ったのは、自分で果物を買うようになってからだった。
食後、息子はおじいちゃんと庭へ消えていった。
「冒険だ」と意気込む割に、やっているのは花への水やりである。
案の定、じょうろの先は花ではなく自分たちに向き、泥んこの水遊びが始まる。
なんでも遊びに変えてしまう息子に、おじいちゃんはどこまでも根気よく付き合っている。
子どもが生まれてから、実家へ帰る頻度が増えた。
孫の顔を見るたび、父と母の顔には皺が増えるようで、同時に若返ってもいるような、不思議な表情が浮かぶ。
かつて帰省のたびに感じていた、
親の期待と自分の現状が噛み合わない、あの居心地の悪さは、
いつの間にか消えていた。
子どもというのは、ただ可愛いだけの存在ではないらしい。
かつてそこにあった親子の距離を、あるいは夫婦の空気を、何の説明もなく繋ぎ直してしまう。
本人はその自覚もなく、
ただ夢中でラ・フランスを頬張り、泥にまみれているだけなのに。
これほど自然に、これほど完璧な仕事をしてしまうとは。
育児の「正解」を探して右往左往している昭和パパとしては、
息子の鮮やかな手際に、ただただ脱帽するしかない。